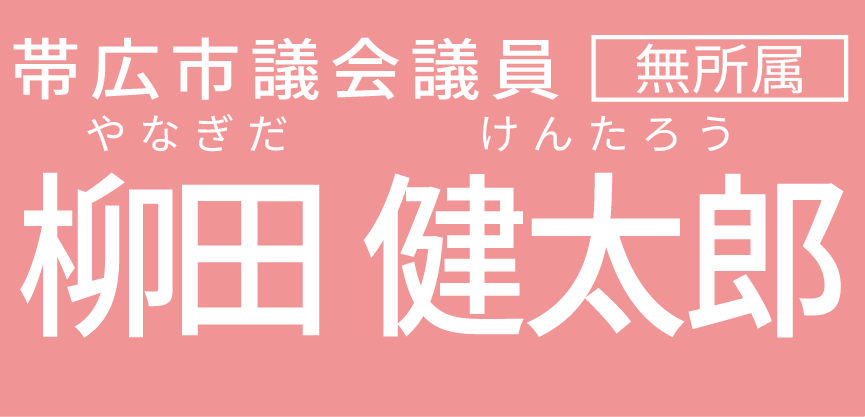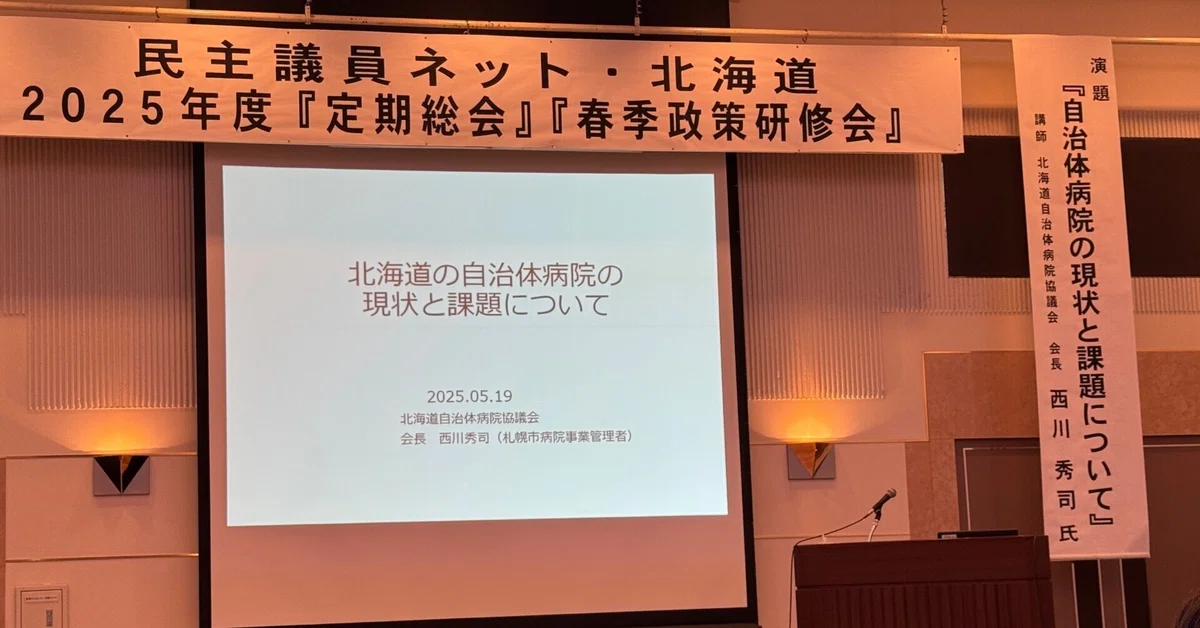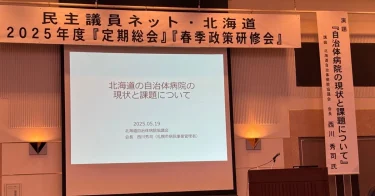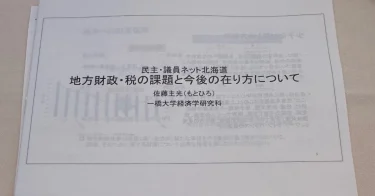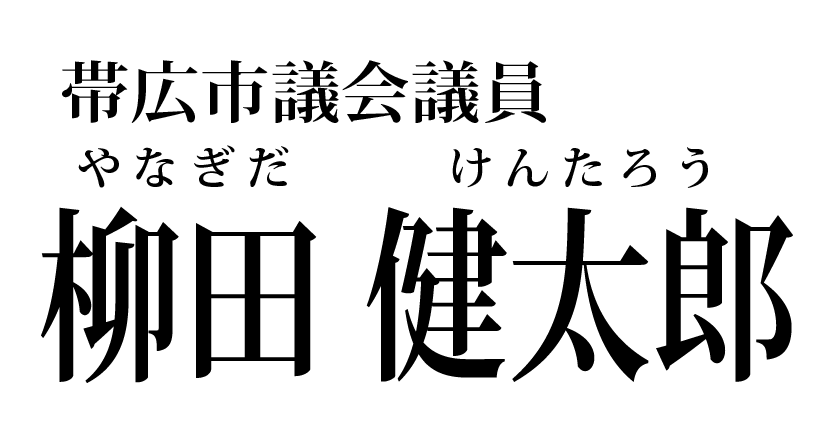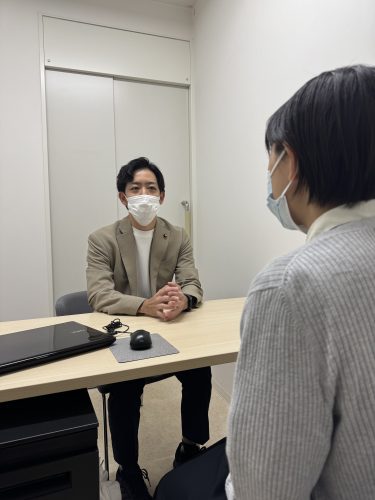帯広市議会議員の柳田健太郎です。
先日、札幌で開催された「北海道の自治体病院の現状と課題について」の研修に参加してきました。今回はその内容を市民の皆さんに共有し、私自身の気づきも合わせてご報告いたします。
なぜ自治体病院が重要なのか?
北海道内には現在、自治体が運営する病院が83施設、診療所が42施設あります。これらの病院は、高齢化が進む地域で「最後の砦」として救急・災害・周産期などを担っており、都市部とは異なる役割を果たしています。
一方で、2008年から2022年の14年間で病院数は約10%、病床数は約20%も減少しているのが実態です。人口減少と医師不足が進む中、地域の医療提供体制は岐路に立たされています。
経営の厳しさと構造的な課題
今回の研修で印象的だったのは、自治体病院の経営構造の厳しさです。
・自治体病院の固定費は約75%、うち大半が人件費
・民間病院でも固定費は約65%であり、業種の中でも極めて高い水準
・2024年度の診療報酬改定(+0.88%)では、物価や人件費の上昇に追いつかず、半数近くの病院が赤字見込み
私たちが普段「病院」と聞いて思い浮かべる施設も、実はその経営は非常にシビアです。
医師確保の難しさと地域連携の必要性
医師不足の問題も深刻です。これまでのように大学医局の派遣に頼る仕組みだけでは限界が来ており、道内全域で医師確保が困難になってきています。これは帯広市にとっても他人事ではありません。
今後は、基礎自治体や広域圏単位での誘致活動、さらには道や国レベルでの支援の仕組みが必要です。病院の経営を一つの自治体だけで抱えるのではなく、「地域のインフラ」として広く支える仕組みづくりが求められています。
医療DXや設備更新の支援がカギに
さらに、電子カルテの更新や医療DXの推進など、新たな投資への対応も急務です。
しかし、これらには一病院あたり数千万~億単位の負担が発生するケースもあり、国や道の支援に加え、市区町村レベルでも支える体制づくりが必要だと感じました。
私の気づきと今後に向けて
今回の研修では、改めて「医療機関は経営体であると同時に公共財である」と実感しました。
帯広市には市立病院はありませんが、十勝の中核都市として、周辺町村の医療体制を支える旗振り役を果たす責任があります。
これからも、
・医師確保への積極的な取り組み
・病院機能の分化と広域連携
・診療報酬と現実のコストのギャップ解消
・社会的インフラとしての医療支援
といった視点をもとに、市政の中でしっかりと議論してまいります。
医療が持続可能であるために、そして誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、引き続き取り組んでいきます。