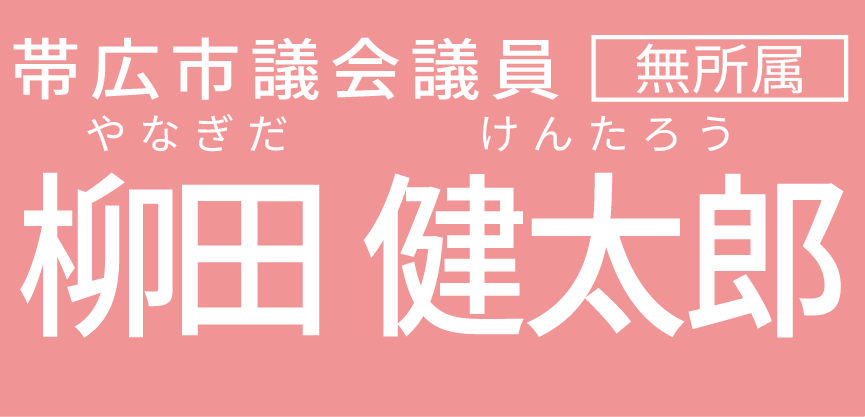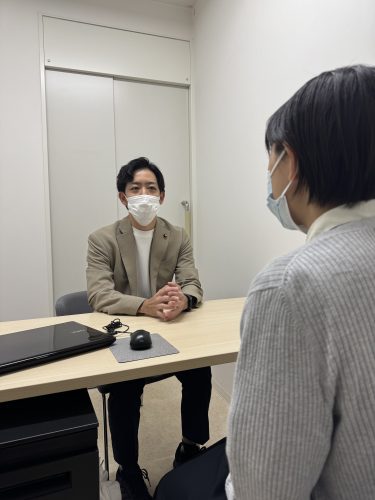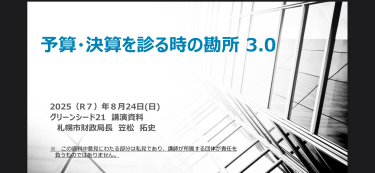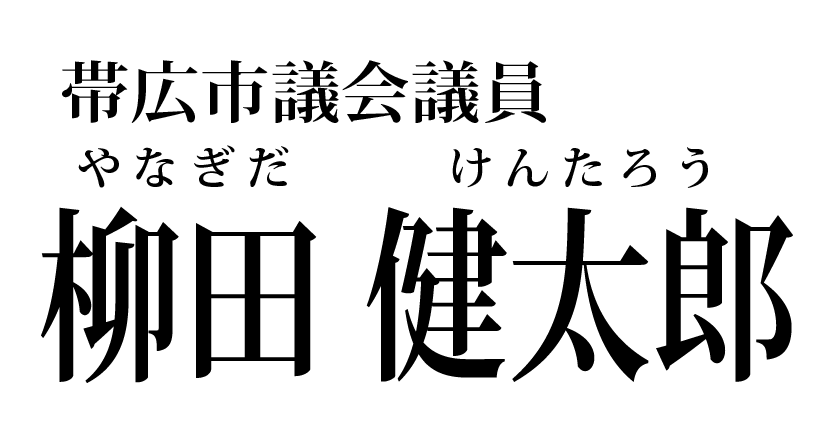こんにちは。帯広市議会議員の柳田健太郎です。
今回は、大阪府吹田市で実施されている「フードドライブ」について視察してきました。
食品ロス削減の取り組みとして全国的にも注目されており、行政と市民が連携して支え合う仕組みを間近で学ぶことができました。

■ 食品ロス対策から始まった行政の挑戦
吹田市では、平成28年に市議会で「食品ロス削減」をテーマに議論が行われたことをきっかけに、翌年の環境教育フェスタで初めてフードドライブを実施しました。
市民の要望を受け、令和2年度からは夏と冬の年2回開催という定期的な仕組みへと発展。
「家庭で余った食品を集め、子ども食堂や福祉団体に届ける」――このシンプルな活動を、行政が継続的に支えている点が大きな特徴です。

■ 市民が主体、行政が支える仕組み
市内4か所(市役所環境政策室・ラコルタ・のびのび子育てプラザ・浜屋敷)に回収拠点を設け、
市民が未開封で賞味期限内の食品を持ち寄ります。
集まった食品は、まず子ども食堂・地域支援センター・社会福祉協議会へ分配し、余剰分は「ふーどばんくOSAKA」へ提供。
まさに「食を通じた地域の循環」が形成されています。
担当は環境政策室の職員2名。
市報・HP・LINE・デジタルサイネージなど多様な媒体を使って呼びかけ、市民の協力によって成り立っています。
■ 数字で見る吹田市の実績
令和7年度第1回のフードドライブでは、177品・約40kgの食品が寄せられました。
一方で、令和6年度第2回は222品・約59kgと、年度によって増減があるのが実情です。
市民の関心は一定して高く、活動が地域に定着していることがうかがえました。
内容も多様で、お米や乾麺、レトルト食品に加え、粉ミルクや生理用品など“生活支援物資”としての側面も強まっています。
■ 低コスト・高効果の運営体制
この活動は、職員2名体制・年間約16万円の人件費で運営されています。
備品や消耗品費(のぼり旗・コンテナ・台車など)も年間数万円程度に抑えられており、行政事業としては非常に効率的です。
保管スペースには公共施設を活用し、
「人が自由に出入りできる」「保管場所がある」「利用者が多い」という3条件を満たす施設を拠点に選定。
こうした現実的な工夫が、継続を支えています。
■ 吹田市の独自性と課題
印象的だったのは、フードドライブを「福祉」ではなく「環境政策」の一環として捉えていることです。
食品ロス削減の延長線上に食支援を位置づけ、市民が主体となって社会課題を解決するモデルを行政が支える。
「やさしさを仕組みにする」取り組みと言えます。
一方で、企業からの寄付は令和6年度から直接子ども食堂などへお願いする形に変更され、
行政が関与しない分、寄付の把握や公平性の確保が課題として挙げられていました。
■ 帯広市への反映
帯広市でも、食品ロスの削減や子ども食堂支援は重要なテーマです。
吹田市のように、「環境」からアプローチすることで、市民参加の幅を広げ、持続可能な支援体制を築くことができると感じました。
“支援を受ける人”と“支援する人”の垣根をなくし、
市民一人ひとりが「もったいない」を共有できる地域づくり。
帯広市としても取り組みが可能な点が多数ありました。議会議論に反映させてまいります。