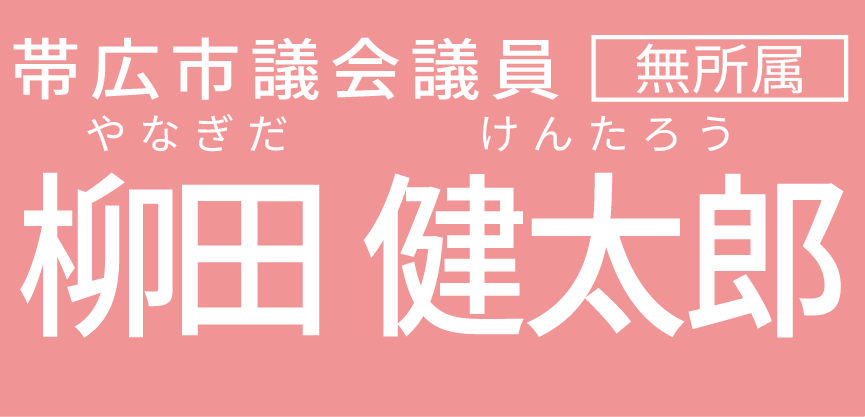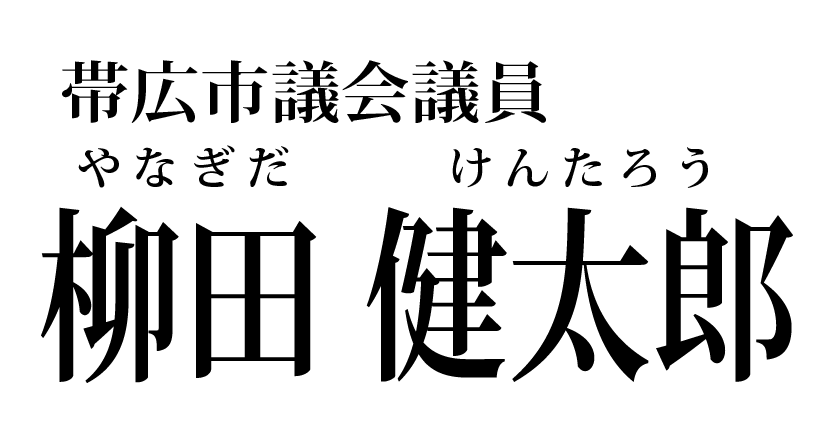一般質問②|人口減少社会に対応した切れ目ない子育て支援
こんにちは。帯広市議会議員の柳田健太郎です。
9月議会一般質問の2つ目のテーマは「子育て支援」です。少子化・人口減少が進む中で、妊娠前から出産・産後、そして保育に至るまで、切れ目なく支える仕組みの必要性について、市民の皆さんにご報告します。
なぜ「切れ目ない子育て支援」が必要なのか
2024年の合計特殊出生率は1.15、出生数は68万6,061人と過去最低を更新。2025年上半期も減少が続いています。国は2022年から不妊治療を保険適用としましたが、依然として自己負担や先進医療にかかる費用は重く、全国の自治体では独自助成を進める動きが広がっています。
本市では北海道と共同で事業を行っていますが、近隣町村より支援が薄いため「帯広を離れて隣町に転居してから帯広市の医療機関で出産する」という声すら聞かれます。人口減少に真正面から向き合うには、「妊娠前~産後」まで一貫した支援パッケージが欠かせません。
私が議場で問いかけたこと(ポイント)
- 不妊治療支援の拡充
年間900件前後の出生のうち、約1割が不妊治療を経由と推定されます。出生数増加に直結する分野として、市独自助成の導入を求めました。 - 妊娠期の負担軽減(エコー費用補助)
帯広市は国基準を上回る6回の助成を行っていますが、現場ではそれ以上の検査が一般的。制度がないため声が上がりにくいだけで、実際には家庭の負担が大きい。人口減少対策として「2人目以降を考える安心感」を与える施策が必要だと訴えました。 - 産後支援の充実
1か月児健診費用が自己負担である現状を取り上げ、国がすでに補助制度を設けていることから、市としても導入を要望しました。また、産後ケアについては利用回数の見直しが進んだものの、より使いやすく改善すべきだと提案しました。 - 相談体制の強化
保健師・助産師・心理士などの専門職配置は十分か、産休・育休による欠員対応はどうか。こども家庭センターとして包括的支援体制を整えることの必要性を指摘しました。 - 保育と待機児童問題
形式的には待機児童ゼロですが、希望園に入れない「潜在的待機児童」は令和7年4月時点で97人。増加傾向にあり、保護者の不安は大きい。保育士の採用だけでなく、処遇改善や業務軽減など離職防止策を重視すべきだと求めました。 - 学童保育のICT環境
学童保育は「預かり」から「学びを支える場」へ役割が変化しています。Wi-Fi環境未整備は時代遅れであり、宿題や調べ学習に対応できる体制整備を求めました。
市の答弁(要旨)
- 不妊治療助成
保険適用分への市独自助成は現時点で考えていない。ただし若年層の申請増加もあり、治療しやすい環境にはなってきていると認識。国や道の動向を注視していくとの答弁でした。 - 妊婦健診・エコー
国基準より多い6回を助成しており、新たな補助制度を導入する考えは今のところなし。ただし転入出時の問い合わせは一定数あると答えました。 - 1か月児健診
経済的支援を目的とした補助導入を検討中であると答弁。 - 産後ケア
令和7年度から利用期間を拡大。今後も利用状況を評価しながら改善を検討。周知もアプリ「子育ておびモ」などを活用し強化すると答えました。 - 保育人材確保
加点措置、復職セミナー、出前講座、奨学金返済支援などを実施中。今後も養成校と連携し確保策を進めるとの答弁でした。 - 学童保育のICT環境
保育室へのWi-Fi整備は未実施。モニタリング調査でニーズ把握を進めていると答えました。
私の提案(アクションプラン)
- 「切れ目ない子育て支援パッケージ」の構築
不妊治療→妊娠期→出産→産後→保育まで一貫支援を制度化。 - 妊娠期の不安解消
エコー費用補助を拡充し「次の子も安心して産めるまち」へ。 - 産後・乳児期支援の厚み
1か月児健診助成を導入し、早期から経済的負担を減らす。 - 人材の“量”より“定着”へ
保育士・学童職員が辞めない環境整備。処遇改善・負担軽減を重点に。 - 学童の学び環境整備
Wi-Fi・ICTを整え「第3の学び場」機能を拡大。
市民の皆さまへ
人口減少に歯止めをかけるには、単発的な事業を積み重ねるだけでは不十分です。妊娠前から出産、保育まで一貫した導線をつくることで、「安心して子どもを産み、育てられるまち」へと進化させなければなりません。
私は今後も、市民の声を丁寧に拾い上げ、持続可能な子育て環境を実現するための提案を続けてまいります。