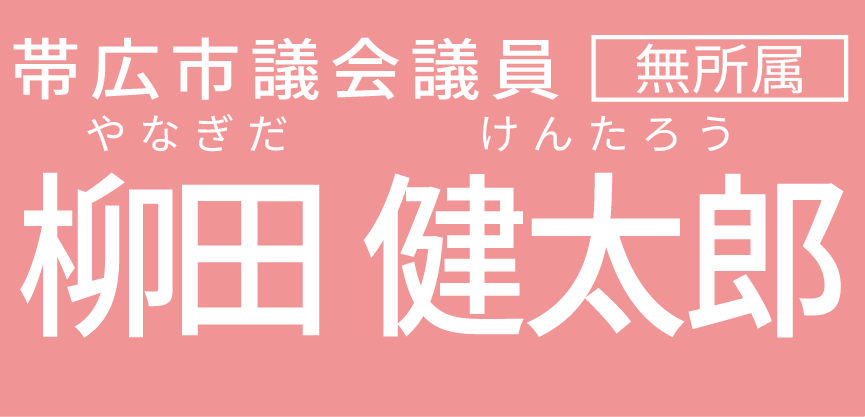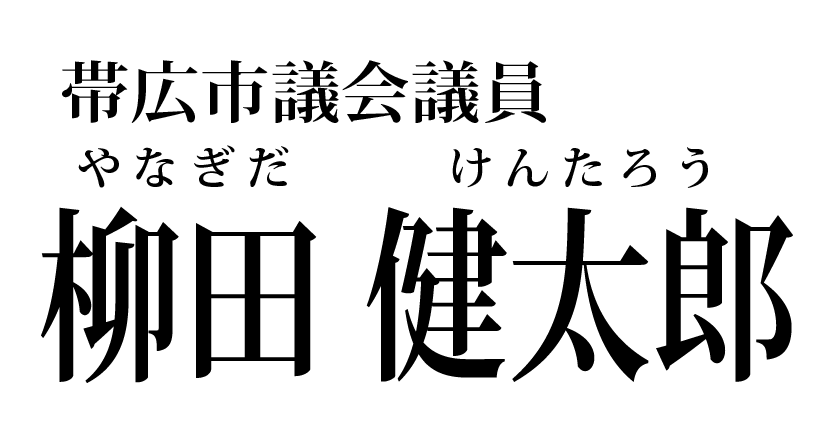一般質問③|救急医療の持続可能性と高齢期の適正な医療提供
こんにちは。帯広市議会議員の柳田健太郎です。
9月議会一般質問の3つ目のテーマは「救急医療」です。地域の生命線である救急体制をいかに持続可能にしていくか、市民の皆さんにご報告します。
救急医療をめぐる現状
救急は「いつでも・だれでも」命の危機に直結する場面で頼れる社会インフラです。しかし全国的に救急需要は増加し、帯広市でも同様の傾向が見られます。
令和6年の救急出動件数は8,981件、搬送人員は7,498人。平均到着時間は8.5分、現場滞在18.9分、病院収容36.1分で、直近では短縮傾向にあるものの、需要増加が続けば体制維持が厳しくなるのは明らかです。
また、不搬送件数は令和元年の1,044件から令和5年には1,913件と倍増。多くは軽症や到着後の辞退であり、不適正利用が深刻化しています。
私が議場で問いかけたこと(ポイント)
- 救急資源の確保
救急車は5台、隊員45名で基準を満たしているが、今後の需要増に対応できるか、市の認識を確認しました。 - 適正利用の促進
本当に必要なときに使えるよう、不適正利用を減らすための周知・啓発を強化すべきだと訴えました。組合HPだけでなく市HPや民間搬送サービスの周知も提案しました。 - ポリファーマシー対策
高齢者の多剤併用による副作用や転倒は救急搬送につながります。本人のQOL低下、医療費増大を防ぐため、市の現状対応と今後の方針をただしました。
市の答弁(要旨)
- 救急車と人員
帯広消防署の救急車は5台、隊員45名で基準充足率100%。現況も同数で体制は整っていると回答。 - 適正利用周知
広域消防組合がHP・SNS・ポスター・イベント等で啓発を実施していると答弁。 - ポリファーマシーの影響
多剤処方や重複処方は副作用や飲み残しを招き、QOL低下・医療費増大につながると認識しているとの回答。 - 現状の取り組み
国保のレセプトデータから対象者を抽出し、相談・指導を実施。400~500万円規模の交付金確保にもつながっている。マイナ保険証で服薬情報を共有できる仕組みも周知していく考え。
私の提案(アクションプラン)
- 適正利用の強化策
- 市HPでも情報を発信し、市民に広く周知
- 民間搬送サービスを必要な方に紹介し、救急車の利用を本当に必要なケースに限定
- 学校や地域イベントでの啓発活動を強化
- 救急体制の将来像を描く
- 「基準を満たしているから安心」で終わらず、将来の需要増を見据えた増強シナリオを策定
- 広域消防との連携や、AIを活用した需要予測を検討
- 地域ぐるみのポリファーマシー対策
- 医師・薬剤師・行政が連携し、処方の重複を早期に発見
- フレイル予防や転倒予防とセットで進め、救急搬送件数そのものを減らす
- データ公開と市民参加
- 救急出動・不搬送・軽症割合の推移を定期的に公表
- 市民と課題を共有し、適正利用を「社会全体の取り組み」にする
市民の皆さまへ
救急はまさに「地域の最後の砦」です。循環器疾患など時間との勝負となる事案では、わずかな遅れが命を左右します。だからこそ、不適正利用を抑制し、真に必要な人に救急を確保することが欠かせません。
そのためには、市民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。加えて、地域全体でポリファーマシー対策や転倒予防に取り組むことで、救急需要そのものを減らすこともできます。
私は今後も議会を通じて、「救急の適正利用」と「地域予防」の両輪で救命力を守る仕組みを提案し続けてまいります。