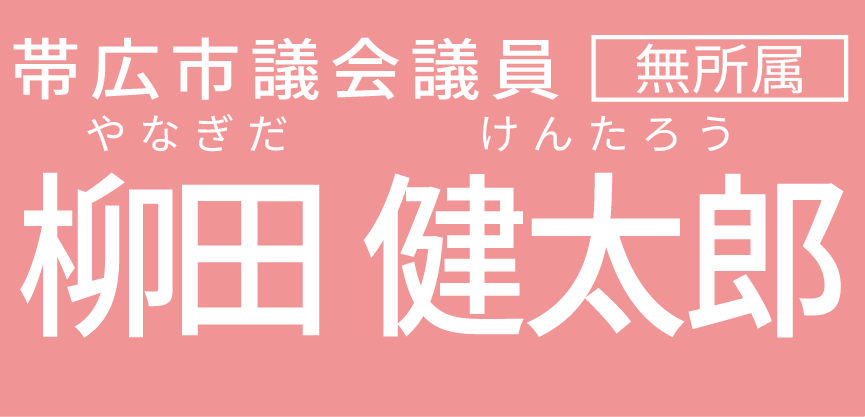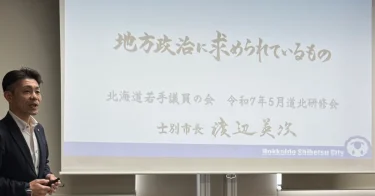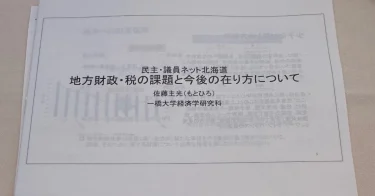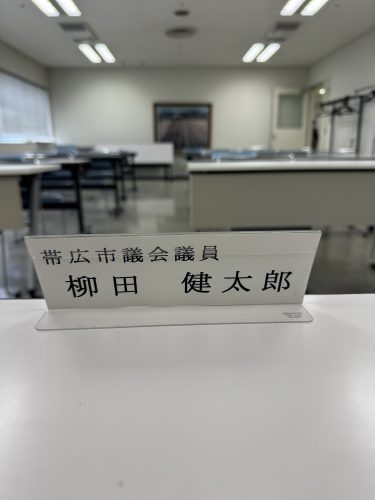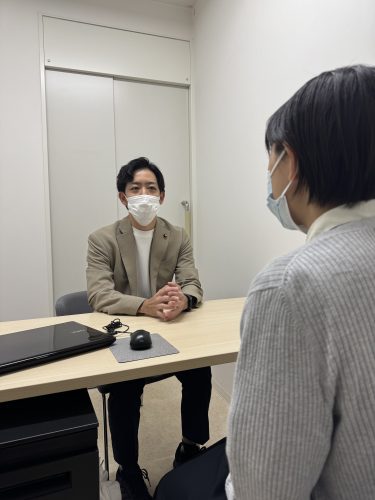帯広市議会議員の柳田健太郎です。
先日、「北海道若手議員の会」道北研修会に参加し、士別市長・渡辺英次さんによるご講演「地方政治に求められているもの」を聴講いたしました。多くの気づきと学びを得る機会となり、改めて自分自身の議員としての姿勢を考える時間となりました。以下、報告として内容を共有いたします。
渡辺市長の姿勢に学ぶ「政治の本質」
講演の冒頭、渡辺市長は「自分が死ぬまでに何をしたいのか、何ができるのか。人のために生きる」と語られました。その姿勢には政治家としての覚悟と誠実さがにじみ出ており、非常に胸を打たれました。
市長に立候補したきっかけには、市議会議員からでは実現できないことへのもどかしさ、執行権を持たない立場の限界、そして地方衰退の真因を直視したいという思いがあったとのことです。
財政構造から見る地方の脆弱さ
士別市の令和6年度予算においては、歳入総額169億円のうち、自主財源は約40億円(24%)にとどまり、依存財源は約128億円に上ります。これは北海道において地方交付税不交付団体が泊村のみであることとも重なり、多くの自治体が国の財政と不可分な関係にある現実を示しています。
これは帯広市も同様です。

地方が抱える構造的課題と「対症療法・原因療法」という視点
「すべての要因は人口減少に集約される」と市長は語っておりました。地方の衰退、財政の逼迫、産業の停滞、教育や医療の縮小、すべての根本にあるのは人口減少であり、それに向き合う現在の多くの施策は医療でいう「対症療法」に過ぎないというのです。
この考え方には非常に共感です。多くの自治体が実施している施策は、目の前の症状を緩和するための対応が中心であり、本質的な原因に踏み込めていないことが多いと、私自身も感じています。

少子化問題の「本当の原因」と向き合う必要性
少子化白書においても、実は出生率低下の主要因は「未婚化」であり、そこには経済的不安・将来不安による結婚回避があるとの分析があります。つまり「結婚できない現実」が背景にある以上、そこに政策的資源を投入すれば、少しずつでも結果に結びつく可能性がある。これは、まさに「原因療法」と言えるアプローチだと感じました。

士別市の取り組みに学ぶべきこと
市長は、士別市において介護人材の確保支援などを行っていることにも触れていました。私はそれに対して「失礼ながら、それもまた対症療法の一つ」と捉えたうえで、だからこそ問いを持ちました。
こうした施策は、どのような財源で実施されているのか?
そして、どれほどの成果を上げているのか?
→渡辺市長は正直に対象療法であることは認めつつもやらないよりはマシということをおっしゃっていました。
施策の評価と、原因へのアプローチのバランスをどう取るか。これはすべての自治体が直面している課題だと感じます。
ふるさと納税の「光と影」
ふるさと納税についても、非常に本質的な議論が展開されました。「地方の財源確保」という建前のもと、実態は高所得者層に有利な制度設計であり、結果として地方同士の競争、ゼロサムゲームになっているという指摘。私自身も、都市部と地方の格差を是正するための仕組みが、かえって別の格差を生んでいないか、再検証すべきだと感じました。

最後に
「地方の衰退は地方の責任ではない」「国の制度と政策の誤りが原因であることも多い」。渡辺市長の言葉は、地方議員としての私たちに深い問いを投げかけます。
今後、私たちは“対症療法”であるからといって手を止めず、同時に“原因療法”の議論を後回しにせず、両輪での政策展開が求められると感じました。
これまでの自分自身の政策提言の多くが対症療法的発想がベースとなっていたことを反省し、今後は対症療法×原因療法の視点での政策提言につなげていき、帯広市が寄り寄り方向に進むよう働いていきたいと思います。