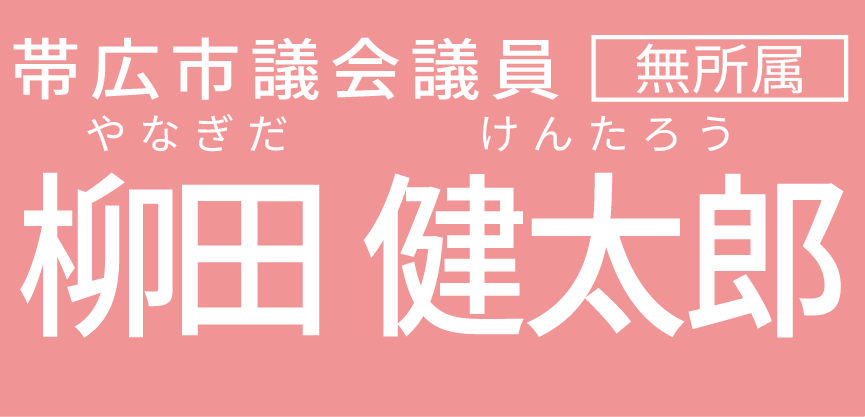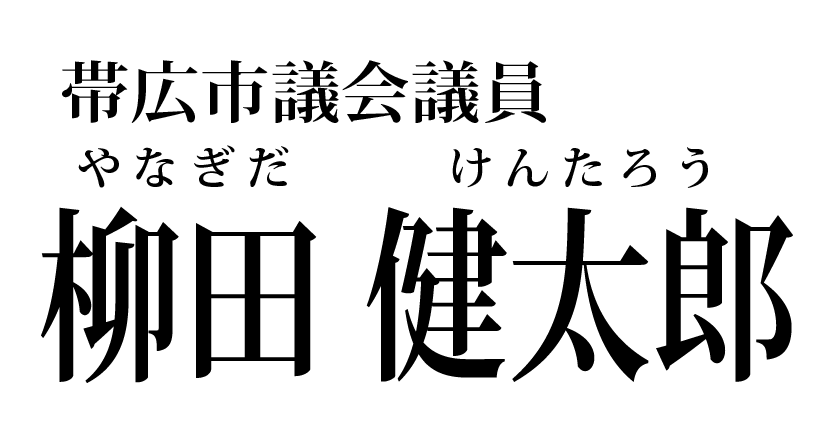帯広厚生病院は地域の最後の砦
帯広厚生病院は、十勝圏域で唯一の「地方センター病院」として位置付けられ、三次救急を担う重要な拠点です。
救急・小児といった採算が取りにくい医療部門を引き受け、地域全体の医療を守る最後の砦として機能しています。
こうした不採算部門を対象に、市と十勝管内18町村が共同で支援を行ってきました。
市の補助とモニタリング体制
令和6年度における帯広市の負担額は2億1千万円。
市は毎年、帯広厚生病院が開催する運営委員会に委員として出席し、不採算4部門を含む全体の収支報告を受けています。
その場で補助金の使途を確認し、適正に執行されていることを確かめています。
単にお金を出すだけでなく、市として責任を持ってモニタリングを続けているのです。
他の病院への支援状況
一方で、帯広市内には厚生病院以外にも不採算部門を担う病院が複数存在します。
市はこれらに対しても、病院群輪番制を通じた二次救急医療体制の維持・確保のため、帯広協会病院、帯広第一病院、北斗病院、開西病院、協立病院に対し支援を実施しています。
また、小児救急医療体制の維持・確保については、道の補助制度も活用しながら帯広協会病院に補助を行っています。
つまり、厚生病院だけに支援が集中しているわけではなく、二次救急や小児救急という観点では幅広い病院を対象に補助がなされています。
周産期医療に残された課題
しかし、今回の議会質疑を通じて見えてきたのは「周産期医療」の扱いです。
厚生病院は十勝全体の出産の約3割を担っていますが、残りの7割は他の医療機関が担っています。
ところが、現行の補助制度では周産期医療に対する支援は厚生病院のみ。
市内の他の病院で出産が担えなくなった場合、その分はすべて厚生病院に集中してしまいます。
これは地域全体の医療バランスを崩し、周産期体制が脆弱になる大きなリスクです。
国のスキームと今後の方向性
総務省は「病院事業の地方財政措置」という形で、医療機関への支援スキームを通知しています。
市はその仕組みを用いて厚生病院に補助を行っていますが、同じように周産期医療を担う他の医療機関に対しても、支援の枠を広げていく必要があるのではないでしょうか。
私の提案と要望
私は議会で、厚生病院を軸に据えつつも、他の医療機関に対しても今後の予算措置を検討するよう強く求めました。
少子化が深刻さを増す中で、安心して出産できる体制を維持することはまちづくりの根幹です。
リスクを分散し、地域全体で命の誕生を支える仕組みをつくることが必要不可欠です。